
2024年3月修了生(5期生)
阪本菜津代 2024年3月修了生

Q1:現在の仕事の内容
A1:高齢者福祉事業、児童福祉事業、飲食事業等々を運営している会社を経営しています。
Q2:入学の動機
A2:仕事柄、地域では様々な地域活動を行っています。地元をよりよい街にしたいという思いが強く『まちづくり』について学びを深めたいと考えました。また、自分自身は感覚人間ですが、多くの人と接する中で自身の思考を適切に言語化することが大切であると考え言語化能力を高めたいという思いもありました。さらに、組織の中で人を育てるにあたり「やればできる」という姿を見て育って欲しいという思いもありました。
Q3:入学して良かったこと
A3:授業は非常に楽しく、何より学ぶことが楽しかったです。
授業では活発な議論が交わされ、個性的な学生が多く、それぞれの意見を聞くのがとても興味深い日々でした。自分自身は、入学当初、授業で発言することもままならない状況でしたが、徐々に馴染んできた頃には学生生活を満喫していました。
そして、新しい世界で、かけがえのない時間を過ごし、沢山の学友や素敵な先生方々に出会ったことはとても良い刺激になりました。社会人大学院では、20歳代、30歳代の若い世代から少し年配の方まで幅広い年齢層が在学していて、皆がそれぞれのフィールドで活躍しています。このような環境の中、知らないことが一杯で日々発見があり、いかに狭い世界で生きていたのかが実感出来、何を聞いても何をしても面白かったです
Q4:将来の夢
A4:私たちの学びに終わりはありません。この経験を今後の人生に活かしていきたいと思います。先ずは、新たな視点から「まちづくり」を考えて実践していきたいと思っています。そして、新しいチャレンジに向けて頑張りながらも研究は続けたいと思います。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:大学院に少しでも興味を持たれたのであれば、是非チャレンジしていただきたいです。社会人であれば、先ずは時間的なことを一番心配されると思います。大丈夫です。色んな障壁は乗り越えることが出来ます。
大学院は、何かを学ぶ場というより、研究をするところです。先生から課題を与えられるところではなく自ら問いを立て問題提起し、研究を進めていきます。私は、研究をするということが理解できていず論文作成に当たっては、先生方々に随分ご心配をおかけいたしました。自分の研究が社会貢献につながること、そして、残された課題は次の研究テーマになっていくことが、修士論文提出間際にやっと理解が出来たように感じます。楽しかった学生生活の中で、準備不足が招いた結果の最後の強烈な追い込みでは「もうダメかも知れない」と心が折れそうになりました。それもこれも全ての経験が何にも代え難い宝物になっています。今は、お世話になりました皆様、応援してくださった皆様への感謝の気持ちで一杯です。
挑戦あるのみです。
小西政宏 2024年3月修了生

Q1:現在の仕事の内容
A1:26歳の時に市議会議員に初当選以後3期務め現在は県議会議員として地方自治に係る仕事をしています。
Q2:入学の動機
A2:地方自治に係る立場として、様々課題を解決する為には更に専門的知識を持ち合わす必要があると考え入学しました。
Q3:入学して良かったこと
A3:様々な講義を通じて物事をロジカルに考えれるようになりました、加えて様々な知識を有する院生と交流できたことが財産となりました。
Q4:将来の夢
A4:大学院で得た知識を活かし、住民の「幸せ」を構築する為に、和歌山県橋本市における課題解決を行ない、ひいては日本の課題解決に繋がることに私自身の命を燃やし続ける事が私の夢です。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:仕事との両立は大変ではありますが講義等を通じて様々な人とのつながりや出会いがあります、様々な人との出会いは様々な知識との出会いでもあり人生における宝物となりました。
何より社会人になってから学べることにとても「幸せ」を感じることが私はできました、
もし入学に悩まれている方は入学し人生における「幸せ」を感じて頂きたいと思います。
森崎匠哉 2024年3月修了生
-300x300.jpg)
Q1:現在の仕事の内容
A1:地方自治体で行政職員として勤務しています。
Q2:入学の動機
A2:これまで行政職員として仕事をする中で、民間企業への出向の際、普段とは違う業務や多様な価値観に刺激を受けた経験が大きなきっかけの一つとなっています。
また、これからのキャリアにおいてステップアップのためには、別フィールドで働く方の考えを吸収することや、都市経営についてしっかりと基礎から学ぶことが重要になると考え、都市の課題解決、特に自分自身が課題意識をもっていたまちづくりについて研究できる本学に入学を決めました。
Q3:入学して良かったこと
A3:何よりも多種多様なフィールドで働く同級生や先生方との交流や繋がりが財産となりました。同級生とは職種や年齢を超えてざっくばらんに話しあえることができ、先生方は講義中だけでなくそれ以外の場でも分け隔てなく意見交換をしていただけました。
また、私は学部生の時は卒業論文を書く機会がなかったのですが、ただ修士論文を提出するのではなく、生徒の課題意識を尊重してくださる先生方の指導のもと研究を行い、論文作成に重要な考え方を学びながら、最終的に修士論文を完成させることができたことは何事にもかえがたい経験となりました。
Q4:将来の夢
A4:大学院の2年間で得られた繋がりや知識、身に着けた考え方をもとに、今後の業務に活かすだけでなく、大学院を卒業した今の自分にしかできないアプローチをもとに、幅広いフィールドで活躍できるようになっていきたいと思います。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:ぜひこの2年間でしか得られない経験を堪能してもらえばと思います。社会人になってからどうしても縛られてしまう年齢や職種といったハードルを簡単に飛び越えて、フラットな状態で話すことができることが社会人大学院の最大の強みの一つだと思います。梅田という好立地のキャンパスで、様々な立場の方と同じ目線で切磋琢磨しながら学生生活を過ごせる機会は中々ありませんので、是非飛び込んでみてください。
西川明宏 2024年3月修了生

Q1:現在の仕事の内容
A1: 地方自治体の行政職として勤務してきました。これまで、地域における市民協働・まちづくり・教育振興や、予算・決算・会計に関する業務に携わってきました。
Q2:入学の動機】
A2:学校の統廃合に関する仕事に従事した際に、少子高齢化が進む現代社会において、まちづくりと密接に関わり、自らが勤務する自治体のみではなく、広く社会的な、現代的な課題であることを実感しました。
全国や世界で様々な方法で行われている地域社会の課題解決や活性化の取組みも含めて、現場や業務で経験したことだけではなく、学術的な面からもまちづくりについて学びたいと思い本大学院に入学しました。
Q3:入学して良かったこと
A3:まずはカリキュラムの幅広さが良かったです。1コマ50分で裾野が広い数多くの講義を履修でき、これまでの仕事や社会経験のなかで関わらなかったり、自分では興味が持てなかったりした分野にも触れることができ、視野や興味関心が広がったと思います。内容としても、実務的に役に立つものから、政策的・概念的な少し大きな視点のものまで様々でした。
また、様々な経験、立場の同級生の皆さんとの交流も新たな視点や発想、気づきを得ることに繋がり、大変楽しく、学びとなるものでした。
Q4:将来の夢
A4:自治体職員として、大学院で紹介されていたような、人口減少社会におけるまちづくりの好事例、先進事例となるような新たな取組みを創出し、社会に発信していけるような仕事をしていきたいと思います。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:社会人大学院ということで、学部時代とは異なり、様々な年齢や立場、経験のある方々と同級生になり、ネットワークができ、同じ目標に向かってともに学ぶことは、自分の人生の引き出しを増やすという意味で非常に有意義だと思います。仕事や社会生活との両立が難しいと感じるかもしれませんが、周りも同じ社会人なので、助け合い、励まし合いながら履修を進められますし、大学院の場所も通学・交流にとても便利ですので、皆さんの新たなチャレンジの最適なステージとして強くおすすめします。

2023年3月修了生(4期生)
高山英夫 2022年3月修了生

Q1:現在の仕事の内容
A1: 大学院入学時までは地方自治体の建築技術職として、30数年勤務していました。
現在は、当大学院のゼミでの研究や行政での経験を活かし、地域問題を解決できるようなコンサルタントになることを目指し準備を進めています。
Q2:入学の動機
A2: 40歳後半頃から、建築・都市計画・景観行政などの経験を、行政とは違うアプローチで社会に貢献できないかと考えておりましたが、仕事もおもしろく時間が過ぎていきました。3年ほど前に学術的な面からも知識を補強したいと思い、「都市経営研究科」がある当大学院が目に留まりました。入試説明会に参加したところ、都市の課題を様々な視点から解決できるプロフェッショナルを養成する大学院であることが分かり、私の目指すべきものと合致したことから入学したいと考えました。
Q3:入学して良かったこと
A3: 都市経営に関わる経済学や公共経営など、深く知らなかった分野を学ぶことができたとともに、論文作成ではデータなどの根拠に基づき論理的に考える力や、絶えず疑問を持って世の中を見ることができるようになったと感じています。
また、社会人大学院ということで、様々な経歴の方とお出会いし、知識や考え方の幅も広がったと感じます。何よりも大学院に来られている方は何事にも前向きで、力をもらうことができました。
Q4:将来の夢
A4: 私が住んでいる地域では、人口減少や空き家の増加など元気がない状況が見られます。ここで学んだことをまちづくりに活かすことで、少しでも地域が元気になり、住んでいてよかったと思うようなまちになればと考えています。
Q5:後輩へのメッセージ
A5: 社会人大学院は、実務的研究の習得はもちろんですが、それとともに研究を通して様々な人たちとの出会いや繋がりができます。また、苦労をともにした学友達はこれからの人生において大きな宝物となると思います。
働き始めてから、いまさら勉強するのに抵抗がある方もいるでしょう。私もそうでしたが、一歩を踏み出すことにより、その後の人生の幅が大きく広がったと実感しています。
ぜひチャレンジしてください。
領家誠 2023年3月修了生
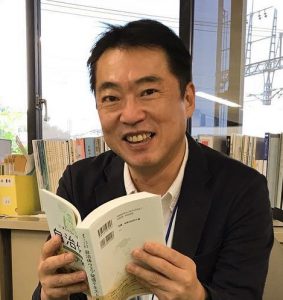
Q1:現在の仕事の内容
A1:大阪府庁に30年ほど勤務し、3年前に人材公募があり生駒市役所に転職しました。地域コミュニティの活性化、市民活動支援、DX・スマートシティ、SDGs、ゼロカーボン、公民連携、農林業振興、商工観光振興と広範な分野を所管する部の部長を務めています。
Q2:入学の動機
A2:大学で講義したり、研究プロジェクトでリサーチャー等になり論文や著作を書くようになって、大学中退の私としては、一度、しっかり論文の指導を受けたいと思っていました。
あとは、タイミングと研究テーマだったんですが、テーマも見つかり、入学資格審査は1年前に通過していたのですが、転職で一年遅らせ入学しました。本学は創造都市の頃にワークショップの講師で一度、話にきていた縁もありましたし、コロナ禍でもあり、仕事がどうなるわからない状況で通勤と通学の便がよかったのも選んだ理由でした。
Q3:入学して良かったこと
A3:講義のテーマもこれまでのキャリアと関係が深いものも多く、社会人の経験を経ての学びは、現役の学生の頃とは各段に違うなと感じました。現職との関係でも即、活かせたことも多くあり、今後に向けての気づきも多く得られました。修了論文の事例調査では、多くの情報だけでなく貴重な出会いも多くありました。動機の一つだった論文の指導も丁寧かつしっかりとしていただき目的を達成できました。
Q4:将来の夢
A4:これまで、100件を超える新規事業、組織の創設、計画策定などに携わり、商工、福祉、健康医療、大型開発など多分野に渡る経験をさせてもらいました。また、産学公民のコミュニティ、ベトナムやタイでのプロジェクトなど社会活動も実施しており、こうした経験に本学での学びをプラスして、中小企業支援、事業立案、自治体の政策形成、公務と社会活動との両立などについて、後進の公務員や公的支援機関の皆さんに伝えていき、少しでも還元できればいいなと思っています。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:私は、新しい仕事に向き合うとき、目の前にある仕事は「どれほど広く、どれほど深いのか」を探るようにしています。そのためには、多くの知識と経験の引き出しが必要となります。また、社会人になっての学びは、普段の課題意識を整理するには絶好の機会になります。とかく短時間に理解できる「見え方」が重視される世の中にあっても、「事の本質」は、普遍の価値だと思います。こうしたことを学ぶ機会として大学院は貴重な経験と財産になると思います。ぜひ、チャレンジしてみてください。
中島潤 2022年3月終了生

Q1:現在の仕事の内容
A1:地方自治体の行政職として働いています。
Q2:入学の動機
A2:コロナ禍で、自分のことを考え直す時間があり、今後の業務に役立つように文章読解能力や文章作成能力を上げることができればと思い受験しました。
Q3:入学して良かったこと
A3:大学院生活はとても貴重な経験ができた2年間でした。知識を習得することの大切さや論理的に考えることを学び、論文を書くにあたっては自分の疑問を追求し、何を知りたいかを深く考えることを学びました。また、同級生と過ごした時間も大切な思い出です。世代や職種を超えた出会いがありました。
Q4:将来の夢
A4:自分の働いている街の住民の方に住んでいてよかったと思ってもらえるような街づくりに貢献できたらうれしいです。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:受験するかどうか迷ったときは、ぜひ受験してみてください。勉強についていけるか不安で受験するか悩み、合格したときも入学するか悩みました。仕事との両立は大変でしたし、授業で分からないこともありましたが、同僚や同級生、先生方に助けてもらいながら、何とか修了までたどり着くことができました。本当に大変だった2年間でしたが、やり切れたことが自信につながりました。
2022年3月修了生(2期生)
木村貞基 2022年3月修了生

Q1:現在の仕事の内容
A1:建築設計事務の代表として、建築設計・デザインのみならず、基本構想計画やプロジェクト企画の立案、まちづくりや不動産コンサルティング、PM・CM業務など、建築プロジェクトを多角的に推進させています。
Q2:入学の動機
A2:近年、建築設計業務が多様化され、建築デザインや技術的スキルに加え、運営手法やアカウントなどが相対的に関わる総合的な提案力が必要とされている中、当研究科の特色である「都市の課題解決を支援する」という実践的講義プログラムが充実されていること、特に公民連携事業(PPP/PFI)による都市再生手法などをテーマに都市や地域の分析・研究ができることは、建築や都市をあらゆる視点で捉え、新たな知識を得る絶好の機会と考え、入学を志望しました。
Q3:入学して良かったこと
A3:あらゆる角度から繰り広げられる各講義プログラムにより、都市経営の本質をリアルに学ぶことができたこと、また修士論文制作においては、先生方によるリアリティ溢れる手厚いご指導から、研究の真意や手法を得ることができ、自身の課題解決に一歩でも近づけたことに感謝の言葉しかありません。加えて、先生方や戦友とも呼べる良き同期生との出会いは、今後の人生に大きな影響を与えてくれる最良の機会となり、かけがえのない大きな財産となりました。
Q4:将来の夢
A4: 今後は全国、特に地方の公民連携の公共開発事業において、建築設計業務の職域を超え、プロジェクト全体を見据えた構想計画段階から積極的に関わり、建築設計事務所ならではのスキームデザイン業務を推進したく思っています。これらを通して少しでも質の高い公共事業が遂行されることにより、地方創生や活性化実現の一端を担えることができれば幸いです。
Q5:後輩へのメッセージ
A5: 論文を制作することで、自身の持たれる課題解決の糸口を確実に見いだされると思います、が、何より、普段の物事の捉え方が広がり、深まるような、一つアップデートされた自分自身を知ることができると確信しています。これが醍醐味ではないでしょうか。また、この濃密な二年間で得た知識や同期生、諸先輩との出会いは、今後の人生において大きな影響を与えることは間違いありません。是非とも大きくチャレンジされ、アップデートされたご自身、そしてかけがえのない仲間たちと出会ってください。

2021年3月修了生(2期生)

生田達也 2021年3月修了生
Q1:現在の仕事の内容
A1:ホテルマンとして接客業に26年間従事し、行政は大きな意味での市民への「おもてなし」という信念のもと、現在は市議会議員として邁進しております。
Q2:入学の動機
A2:自分自身に、法と政策の視点から、地方自治を考える能力と知識が不足していることを認識し、都市経営分野についての専門知識を身につける必要があると感じていました。そんな折、創造都市研究科を修了した同僚議員から紹介を受け、本研究科が十分に学習ができ、行政や政策に関する実践的な知識や幅広い活用能力を身につけられると感じ、修学したいと考えるに至りました。
Q3:入学して良かったこと
A3:論文の作成や研究を通して物事をロジカルに考えれるようになりました。結論を裏付ける根拠や背景、ロジックを肉付けするデータや事例という順番で、論理的に筋道を立てて主張や受け答えができるようになったと思います。
しかし、一番良かった点は、社会人が主ということもあり、豊富な知識や経験、また異なる視点や熱意を持つ院生と触れ合えることができたということです。
Q4:将来の夢
A4:将来ではないのですが、「豊かに暮らすため」を目標(夢)とし、イノベーションによる持続可能な行財政運営の確立に貢献したいと思っています。この想いを実現させるためには様々なスキームが必要となりますので、たくさんの経験を積み、更に知見を広げてまいりたいと思っています。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:スケールメリットを通じたより有効的な投資、そして大学の魅力、社会人育成能力、そして研究能力の成長を図るのが目的で、大学が統合され大阪公立大学が誕生いたします。技術革新や市場の変化に対応するためには、これまでの知識やスキルのアップデートと、新たな知識とスキルの習得が欠かせません。それには自らが学びの機会を作ることが重要で、新たな大学は有意義な院生生活を送ることが出来ると思います。
様々な挑戦をし、成長を感じる2年間にして下さい! 共に頑張りましょう。

宮本 香 2021年3月修了生
Q1:現在の仕事の内容
公認会計士として、監査法人に努めています。主にパブリック関係の団体様を対象に、ガバナンス強化や新たな制度導入等の支援をしております。
Q2:入学の動機
実務家として仕事をしていく中で、なぜ社会は今のような仕組みなのか、もっとより良くなるような考え方はできないのか、と自問自答をすることが多くなってきました。自分で考えてもよくわからなかったので、学問の世界にその答えを見つけようと思い、大学院を志望しました。
Q3:入学して良かったこと
同期の方々のバックグラウンドを聞いたり、授業を受けていたりする中で、これは入学する学科を間違えてしまったかもしれないと思うくらい、多様な方々や授業がありました。
ただ、それはこれまで自分が持っていた知識が、狭く偏ったものであることに気づきました。自分の研究分野は社会の中でどのように位置づけられるのか、そして、研究とはどのようなものであるのかということは、大学院に入らなければ、気づけない視点であり、かけがえのない財産となっています。
Q4:将来の夢
ガバナンスの専門家として、研究を深めるとともに、実務と学問の架け橋となれるような人材となりたいと考えています。社会のニーズにあった行政組織とはどのようなものであるかについて、これからも研究をしていきたいです。
Q5:後輩へのメッセージ
社会人で大学院に進みたいけれど、迷われている方はたくさんいらっしゃると思います。私もその一人であり、大学院に行きたいと思ってから7年迷い続けました。ぜひ勇気をもって足を踏み出してほしいと思います。できない理由はいくらでもあります。でも大学院に入ると、本当に世界が大きく変わります。皆様にもその感動をぜひ味わってほしいと思います。

2020年3月修了生(1期生)

高原浩之 2020年3月修了生
Q1:現在の仕事の内容
A1:米国建築家シーザーペリの下で、国立国際美術館、中之島三井ビルディング、九州大学伊都キャンパスマスタープランを担当し、2004年、㈱HTAデザイン事務所を設立後は、住宅から教育施設、川の駅はちけんや・道の駅みさき・PMO事業の公民連携の建築とまちと人を繋ぐ多様なプロジェクトに関わっています。
Q2:入学の動機
A2:建築の設計は、社会と大きく関わります。持続可能な建築を設計するには、その実現のための技術力だけではなく、地域経済・地域コミュニティーとの関わり方・マーケティングやICT/AIを用いたイノベーションなど、いわゆる都市経営の分野を学ぶことで、建築を都市の一員として捉え、私自身の設計理念 “建築<まち<人”の具現化のための学術的視野を拡げる目的で入学しました。
Q3:入学して良かったこと
A3:1年次には、私にとっては異分野であった経済学・公共経営・自治体会計の分野と実務で関わっていたまちづくり・都市計画・公民連携等の両面から学ぶことができました。そして、何よりも2年次での修士論文の作成においては、大いに悩み楽しく苦悩しながら、指導いただいた先生方をはじめ、特に同ゼミの中浦さんには、プロフェショナルとしての社会貢献への思いとその価値の大きさについて刺激と励ましを頂き、無事終了できました。この大学院での新たな出会いは、私の一生の宝物となっています。
そして、大学院で学んだことの集大成として、修論で取組んだSDGsは、私にとって公私ともに大きな指針となっています。このことで、前述の設計理念、“建築<まち<人“に”<地球“が加わりました。
Q4:将来の夢
A4:2020年、コロナウィルルスの影響で社会は大きく変わろうとしている今、建築家として経営者として、持続可能な社会へ貢献し続けること。具体的には、この夢に向かって日々の設計業務の中でのSDGsの具現化、地域コミュニティーでのSDGs講座や建築学科の学生へのSDGs講義など次世代へつなげて行く活動など、私自身ができることから活動を始め、継続して行くことこそが私の夢=目標です。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:既に多様なキャリアを持ち、社会において大きな貢献を果たされている皆さんが都市経営という人の営みのプラットホームとなる分野で同志として学び、交流することで更に、活動の幅が広がることは、間違いありません。この大学院での学びと交流を大いに楽しみ、時には苦悩しながら、新たな社会へ大きく一緒に貢献して行きましょう。

土野池正義 2020年3月修了生
Q1:現在の仕事の内容
A1:建築設計業界で技術者として40年間以上業務を続けており、現在も建築設計事務所を主宰し、意匠設計、構造設計、工事監理、耐震診断業務と多岐にわたり、官民発注物件を含めて多種多様な用途の建築物の安全安心の為に、日々設計業務に邁進しています。
Q2:入学の動機
A2:都市経営研究科修士課程一期生募集の内容を日経新聞で知ったのは、10月末日であったのを記憶しています。何時かの機会にリカレントをと考えていた時期でもあり、斬新なカリキュラムの内容が動機となりました。
Q3:入学してよかったこと
A3:終了年限は2年間、短時間であるが、非常に内容のある講義、集中講義やワークショップを含めて内容の斬新さは、社会人大学院ならではの経験でした。1回生の終了間際には、レポート提出に追われ、息つく暇も無かったのは、久々の経験でした。院生仲間の輪の広がりと協力意識は、職場でも経験できない2年間でした。東京で行われた論文構想インターゼミへの参加もよい経験になりました。ご指導いただいた先生方の熱い論文指導に感謝しています。
Q4:将来の夢
A4:都市経営について培った2年間の経験をこれからも広い視野を持って、業務に生かしたいと考えています。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:人生で初めての学位論文の執筆、論文構想段階では、『空き家対策と利活用』、『県内産材木材の利用動向と林業の将来性』、『タワーマンションのライフスタイル研究』、『余剰ゴルフ場の発生要因と将来動向』思いつくままに研究課題を抽出しました。論文執筆を始めると、論文の求める文章能力、研究内容が持つオリジナリティ、研究の独創性、研究目標に対しての論証能力等について、自分の力量がいかに不足しているかを気付かされました。アンケート調査回収では、回収率25%と低迷したこと、心が折れそうになりました。論文完成のため、地理情報システム、ジオコーディング、アンケート調査分析手法、ヒヤリングやインタビュー手法、不動産経済学、重回帰分析等々、講義でも得られた知識と手法、考えられるツールを全て論文執筆に生かせたのは収穫でありました。とにかく、論文完成にはアイデア、独創力を養うことを後輩たちへのメッセージにしたいと思います。

藤岡達也 2020年3月修了生
Q1:現在の仕事の内容
A1:在阪の民間放送局で、スタジオセットやCG、テロップなどのデザイン、管理などを担当する「テレビ美術」という部署のマネジメントをしています。
Q2:入学の動機
A2:社会人として「変化」に柔軟に対応していくために、新しい知識をインプットし続けることが必要だとずっと考えていましたので、40歳を超えた頃から「大学院での学び」を渇望するようになりました。一方で会社からは「マネジメント力」を要求されるようになり、それなりに面白くなってきましたので、私としては、大学院か仕事かの二者択一で、仕事を優先する毎日を過ごしておりました。50代に入り「人生100年」という言葉が出てくると、「修士を目指すことと、仕事は、どちらかを選ぶということではなく、両立すればいいのではないか」と思うようになりました。改組したばかりの本学都市経営研究科は、一期生として自分が新たな扉を開くことができるという意味で非常に魅力的で、それが受験の最後の一押しとなりました。
Q3:入学して良かったこと
A3:まずは、梅田という立地です。通学にも、講義後にみんなで飲んで帰るのにも便利です。次に、「都市のイノベーションとサスティナビリティ」に則った1コマ50分のカリキュラムにより、2年という限られた期間で多くの講義を選択することができます。さらには設備です。膨大な図書収蔵量を誇る学術情報総合センターの本を、杉本町まで行くことなく取り寄せられる図書コーナーと、修士論文執筆のあいだ毎日・毎晩お世話になったPC完備の情報処理教室、これらの部屋の光景は、感謝と汗と涙の記憶とともに生涯脳裏に刻まれることでしょう。そして何より、個性豊かで親身に接していただいた先生方との出会い、コース17名の同級生との出会いが、完成した修士論文とともに、一番の私の財産となりました。
Q4:将来の夢
A4:せっかく今回、私なりの「学問の扉」を開けたのですから、さらに博士課程への進学を目指します。その先は…。このご時世、数年先すら予測できませんが、きっと「自らのバージョンアップ」は、少しなりとも成し遂げていると思います。
Q5:後輩へのメッセージ
A5:私は大学卒業後30年で修士になりましたが、そのあいだ特定の学問を学んできたわけではありません。よって立つ「学問的立場」を持たない社会人は、論文執筆において苦労します。それは仕方がありません。しかしながら、社会人大学院生、そして社会人修士は、社会人であることが「武器」です。そしてその使い方は、あなた次第です。一人でも多くの社会人が、大学院に通い新たな知識を得ることで、人生100年時代に充実した人生を送ることができるよう願ってやみません。ぜひともお互い応援し合いましょう。





